大学で学ぶ内容と学び方:公認心理師を目指す高校生が知っておくべき心理学の基礎から応用まで
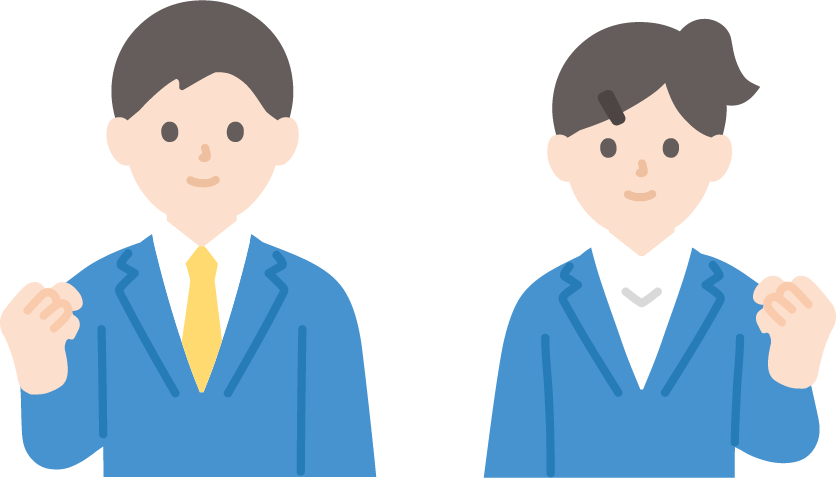
学問としての心理学は、科学的な方法に基づいて人間の心や行動を研究するものです。ポップな心理学が日常のヒントや雑学として楽しめるのに対し、学問としての心理学は、実験やデータ分析を通して客観的な事実や理論を解明しようとするものです。そのため大学では、たとえば行動の仕組みや感情のメカニズムを科学的に学びます。基礎から応用まで段階的に学べるのが大学の魅力です。この記事では、心理学の主要な学びのステップと学習方法について紹介します。
基礎から学ぶ心理学の分野
公認心理師のカリキュラムを提供している大学では、多くの場合、入学してすぐに「心理学概論」という授業があります。この授業では、心理学全体の基礎知識を浅いながらも広く学び、心理学のさまざまな分野への入り口としての役割を果たします。
学年が上がるごとに、心理学の各分野をより専門的に学んでいきます。公認心理師の指定科目における基礎系科目には、たとえば「知覚・認知心理学」「学習・言語心理学」「感情・人格心理学」「神経・生理心理学」「社会・集団・家族心理学」「発達心理学」などの科目が含まれます。
実践に近づく応用心理学
基礎心理学を修得した後は、応用分野へと学びが進んでいきます。公認心理師を目指す場合は、特に臨床心理学やカウンセリングの知識が重要です。
実践につながる応用系科目としては、「障害者(児)心理学」「心理的アセスメント」「心理学的支援法」「健康・医療心理学」「福祉心理学」「教育・学校心理学」「司法・犯罪心理学」などが挙げられます。これらの科目を通じて実際の支援に必要なことを学んでいきます。
実験・調査で身につけるスキル
心理学では、調査や実験を通じたデータ収集と分析スキルが重要です。実際のデータを科学的に分析し、レポート作成やプレゼンテーションで発表する能力も養います。「心理学実験」や「心理学研究法」などの科目がこれに該当し、調査設計やデータの解釈方法を学びます。また、公認心理師の指定科目ではないものの、「心理統計法」もデータを扱う上で非常に役立つ重要な科目です。
演習・実習で学ぶ心理支援
大学の学びの後半(大学によっては早期から)では、心理支援の現場を見学したり、実践家の方からお話を聞いたりする機会があります。「心理演習」や「心理実習」もあり、心理学の知識を実践的に活かす方法を学びます。ただし、学部での心理実習は基本的には見学実習が中心です。
まとめ
心理学の学びは、基礎から応用、さらに実践的なスキルへと段階的に進み、最終的には心理支援の現場で役立つ力を磨いていきます。大学での学びを通じて、心や行動を深く理解する力を養い、将来のキャリアに繋げるための大切なステップです。
